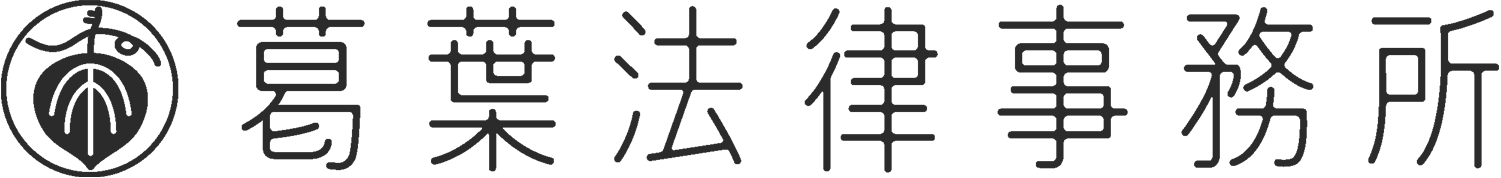取引先が新会社を設立して旧会社の未払金の支払いを拒否したのに対して裁判で新会社から満額の1400万円を回収したケース
事案の概要
X社はM氏が創業した会社で、それなりに知名度のある商品の製造販売をしていました。
しかし、M氏が急死し、M氏の相続人全員が相続放棄をして会社を引き継がなかったため、X社の経営が宙に浮くことになりました。
やむなくX社に残っていた従業員が新しくY社を設立し、X社の事業を事実上引き継いで営業を続けました。
ところで、X社とY社は別法人なので、X社の債務をY社が負担することはないのが原則です。
そのため、X社に材料を納入していたA社は、X社の未払い金1400万円をY社に請求しましたが、Y社からは未払い金がX社の債務であることを理由に支払いを拒否されました。
当事務所の強み
この場合に弁護士が普通に思いつくのは「法人格否認の法理」でしょう。
法人格否認の法理というのは、簡単に言うと、甲法人から乙法人に変わったけれど中身が同じで側だけ変えたような場合には、甲法人の債務を乙法人も負担するというものです。本件で法人格否認の法理が成立すれば、X社の債務をY社も負担することになるので、Y社に対してX社の未払い金を請求できることとなります。
しかし、法人格否認の法理が成立するためにはいくつか要件があり、その中のひとつに「実質的支配者が同じであること」というのがあります。これは、甲法人と乙法人が同じ人物によって支配されている、というものです。
この点、X社の支配者といえるのは創業者のM氏ですが、そのM氏が死亡したためY社に移行したので、X社とY社で支配者が同じであるとはいえないと考えられます。そのため、法人格否認の法理に基づく請求はかなり厳しいと予想されました。
実際、A社は顧問弁護士に相談したけれど請求は難しいと言われたため、過去に依頼したことのある弁護士のツテで当事務所に相談に来られました。
その上で他に請求できる法的構成がないかを検討したところ、Y社はX社と比べて会社の代表者が変わっただけで、商品や店舗、ロゴ等はほぼそのままX社のものを使用していたことから、会社法22条1項の類推適用に基づいて請求できるのではないかと考えました。
会社法22条1項とは、新法人が旧法人の商号(会社名)を続用している場合には、旧法人の債務を新法人も負担するというものです。
本件では、X社とY社は会社名が異なるので会社法22条1項の適用はありませんが、リーガルリサーチをした結果、商号でなくても屋号(店の名前)などが続用されている場合には会社法22条1項を類推適用するという裁判例が見つかりました。
Y社は、X社の頃と同じ屋号を使っていました。そして、店舗、ロゴ、商品、ホームページなどもX社の頃とほぼ同じものを使用していました。
そこで、会社法22条1項の類推適用に基づいて訴訟提起することとしました。
その際、訴訟提起した後にY社が店の名前やホームページ等を修正する可能性があることから、提訴前にできる限りY社がX社の頃と同じものを使用している証拠を集める必要がありました。そのためにはA社から提供される取引関係の資料だけでは不足だったので、当職がY社の店舗に行って外観を撮影したり、商品を買って包装紙やレシートで同じ屋号が使われている証拠を集めたり、Y社のホームページやSNSをX社の頃までさかのぼって掲載写真を押さえたり、食べログなどに掲載されていたX社の頃の店舗写真等を押さえたりして、膨大な量の証拠を集めました。
実際、提訴後にY社からはX社の屋号を使用してないなどと反論されましたが、提訴前に証拠を押さえていたので有効な反論にはなりませんでした(提訴後にY社はホームページなどを修正しました)。
解決結果
尋問も実施した上で、当方の請求を完全に認める判決が出ました。
それに対してY社は控訴してきましたが、高裁でも裁判官から当方の請求が完全に認められる旨の心証が開示されました。
その上で和解協議が行われ、Y社からはいくらかの減額を要望されましたが、当方としては減額に応じる余地はないとして、請求額の満額である1400万円をY社が支払うという和解が成立しました(遅延損害金はカットしたのでY社にとっても和解するメリットはありました)。
他の弁護士との違い
X社からY社に移行した際に代金未払いのまま踏み倒された業者は他にも複数ありました。
そして、当方が訴訟提起した後で、別の業者(Z社)がY社に対して訴訟提起し、しかも既に終結済みであるという情報を得ました。Z社の代理人弁護士も分かったので、その弁護士に裁判記録を開示してもらえないか打診したところ、一切回答できないとのことでした。
そこで、裁判所でZ社の訴訟記録の閲覧謄写を行いました。そうしたところ、Z社も会社法22条1項の類推適用に基づいて訴訟提起していたことが分かりました。しかし、リーサーチ不足で勝ち筋が見えていなかったのか、会社法22条1項の類推適用を裏付ける証拠はほんの数点しか提出されておらず、Y社の主張に対して有効に反論できていませんでした。Z社は裁判の途中から不正競争防止法違反の主張も追加していましたが、タイミングからすると会社法22条1項の類推適用が認められないとなったため苦し紛れに追加した様子がうかがわれました。
結局、Z社の訴訟提起時の請求額は250万円でしたが、解決金50万円で和解していました。しかも、Y社の要望で和解条項の中に守秘義務条項が入れられていたため、Z社の代理人弁護士が一切回答できないと言っていた理由も分かりました。 弁護士が訴訟提起の段階で勝率の高い法的主張を検討できるか、法的主張に沿った証拠をどれだけ収集できるかによって、結果に差が生まれた事案といえるでしょう。